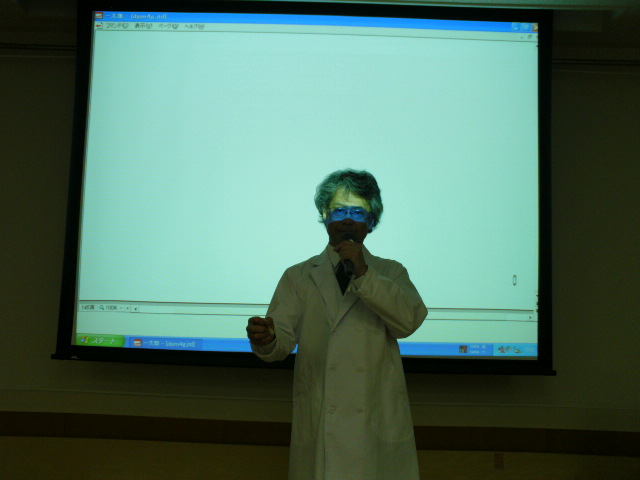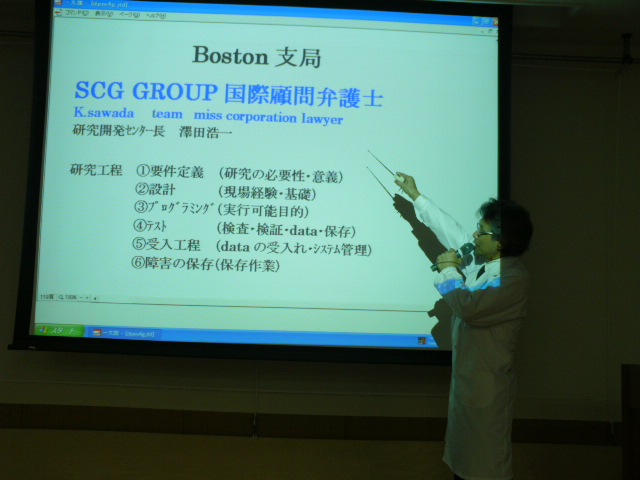実践的国際取引契約に関する法律問題
契約交渉段階における問題
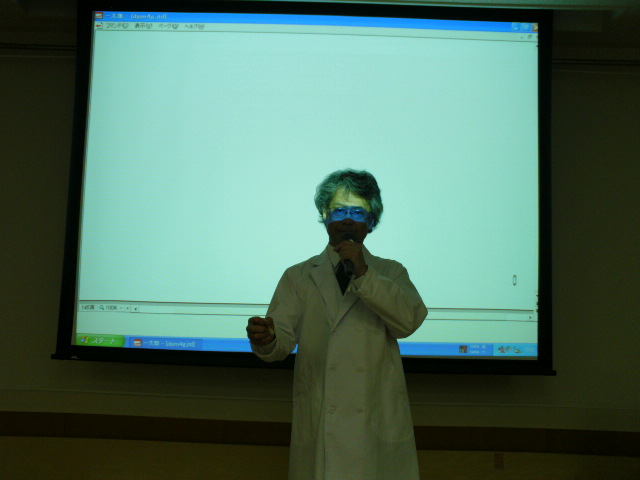
国際取引契約の場合、申込に対して直ちに承諾が行われ契約が成立することもあるが、
契約内容につき当事者間において様々な交渉が行われ、その上で契約の締結に至ることも少なくない。
従って、この交渉段階においても当事者間に法的問題を生ずることがある。
予備的合意
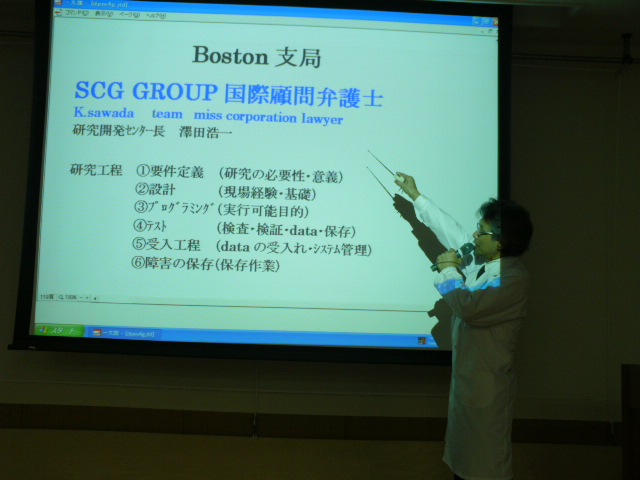
契約についての予備的合意
国際取引契約の成立を期して関係当事者間において交渉が繰り返され、次第に契約内容が固まっていく過程において、
あるステップごとに相互の合意、時には合意できない事項を確認して、次のステップに移るということが行われ、
従って、各ステップでの確認を文書化して確実に期するということが実務において行われる。
こうした契約交渉過程における確認文書の中でも正式契約締結の直前文書は、確認の為ばかりでなく、
各当事者の内部機関(株主総会・取締役会)における意思決定や契約の実施に際して協力してもらう必要のある
外部機関(契約の実施に必要な資金を融資する金融機関)の事前の同意の取付のために必要なことも少なくない。
こうして、当事者間において積み重ねられていく合意は、あくまでも最終的な契約の成立を前提条件とするものであるので、
予備的合意と称される。
予備的合意の後に最終的な契約が成立すれば予備的合意について問題は生じないが、契約締結直前の予備的合意が
行われたものの、予定または期待された事情や条件がうまく実現せず、最終的な契約が締結できない場合、
そうした契約交渉の最終段階における予備的合意の法的効力が問題となることがある。
予備的合意の法的効力が問題となった場合には、その判断の基準となる準拠法を決定して、
その効力を判断しなければならない。(国際取引法要説より抜粋)
予備的合意の準拠法
予備的合意の法的効力を判断するための準拠法の決定に際しては、まず、予備的合意の法的性質を確定し、
それに適用すべき法令中の法選択規制を確定し、その法選択規則を適用して予備的合意の準拠法が決定される。
インドネシア林業開発事件
マレーシアの有力実業家と日本の総合商社との間におけるインドネシアにおける林業開発事業計画についての契約交渉の
最終段階における予備的合意の法的効力が争点の一つとなった。
日本の裁判所は、この予備的合意についての当事者の準拠法に関する明示または黙示の意思が不明であるとし、
主として交渉が行われた場所である東京が行為地と認められるので、法令第7条2項により行為地である日本法が準拠法になること、
並びに、予備的合意の申込が発信された場所が東京であることから法令第9条2項によっても東京が行為地、行為地法である日本法が準拠法
である日本法が準拠法となることを理由として、日本法を準拠法と決定して判断を行っている。 (国際取引法要説より抜粋)
|
契約締結上の過失
契約交渉段階における契約締結上の過失
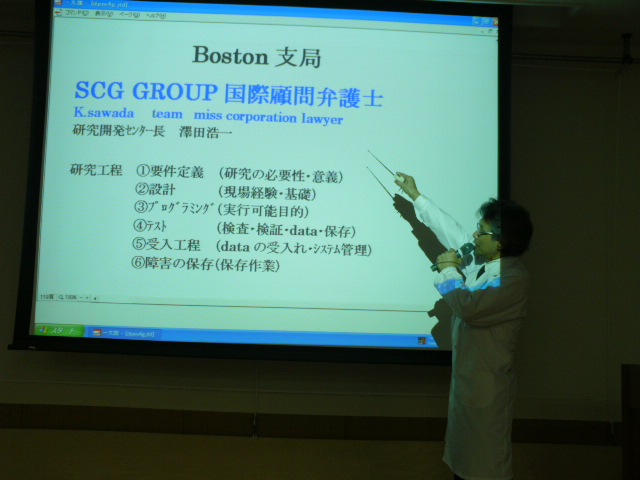
契約交渉段階における契約締結上の過失
予備的合意が契約として成立していない場合であり、契約締結交渉の段階における確認文書に過ぎない場合であっても、
予備的合意が成立するなど交渉当事者間にある程度の緊密な関係が形成されてくると、単なる契約交渉段階からは
一歩踏み込んだものになり、契約準備段階に到達したということができる。
契約準備段階に至った後に、当事者の一方が理由なくy交渉を打ち切り、それによって相手方の契約成立への信頼を
裏切ったときには、その行為を契約締結上の過失であるとして、相手方は、その受けた損害を交渉を一方的に打ち切った
当事者に対して賠償請求することができるかが問題となるところである。
こうした場合にも、国際取引契約についての契約上の過失の正否とそれに対する損害賠償の可否の決定は、
準拠法を決定して判断することとなる。
(1)日本
この問題につき、学説は、契約の原始的不能や無効の場合について展開された「契約上の過失理論」を
契約交渉が準備段階に留まり契約成立に至らなかった場合にまで拡大してきている。
一方、従来この問題につき消極的であった判例も、最近においては、契約準備段階についてまで認める傾向にある。
(2)ニューヨーク州法
ニューヨーク州法の下における事件としては、米国デラウエア州裁判所における事例がある。
(3)ロンドン
英国における類似の事例としては、Donein Productions Ltd. v.E.M.I. Films Ltd., The Times,
March 9,1984がある。 (国際取引法要説より抜粋)
契約の成立に関連する問題
意思表示(申込/承諾)の準拠法
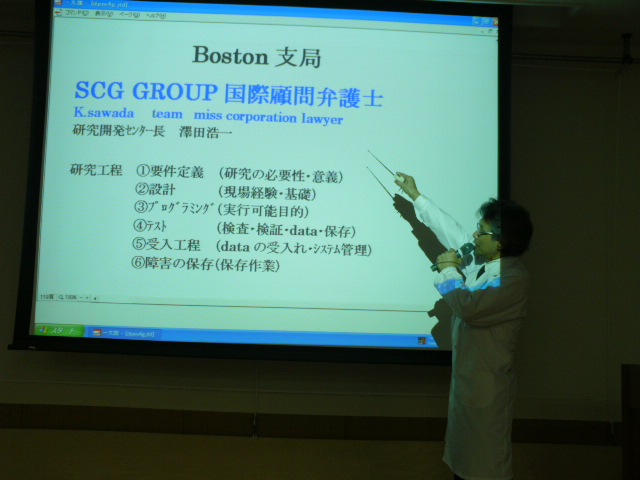
申込または承諾に関連する問題
(1)日本
契約という法律行為の要素である申込や承諾といった意思表示については、それらの成立または効力が、
次のような具体的な事例において問題となるところである。
申込については、ある意思表示が申込となるか否か、申込が効力を生ずるのは、発信によってか到達にによってか、
それとも相手方の了知をまってか、申込の効力存続期間、申込の撤回または取消、申込の失効原因、意思表示の貸しある申込の効力、
申込の内容が可能であり確定しており違法か、申込の解釈などが問題となる。
承諾については、ある意思表示が承諾となるか否か、承諾が効力を生ずるのは、発信によってなのか、到達によってなのか、
それとも相手方の了知をまってか、意思表示の貸しある承諾の効力、承諾の解釈などが問題となる。
国際取引契約に関連するこれらの問題については、渉外的要素を含んでいるので、まずその判断の基準となる準拠法の決定が必要となるが、
多数説と有力説との間に下記のような見解の対立が見られるところである。 (国際取引法要説より抜粋)
多数説;契約の実質の準拠法による
(1)日本
日本における申込並びに承諾は、契約の要素をなす意思表示であり、契約と緊密な結合関係にあるので、
契約の実質(=契約の成立及び効力)の準拠法によるべきあるとしている。
他に多数説として、沈黙が承諾となるかとの問題については、多数説によると、申込において契約の性質の準拠法として
指定された日本法により判断することになり、日本商法第509条が適用されて申込は承諾されたものとみなされることになり、
この場合の取引の相手方である承認の利益保護の観点から妥当ではないとの批判が行われている。
この批判に対して、国際私法の観点からは証拠法規程として、準拠法の内容とはならないものと考えるべきである。
裁判所は、取消不能信用状の条件変更の申込についての準拠法の決定につき、多数説により準拠法を決定しつつも、
準拠法とされた日本商法第509条の適用については、被申込者である承認の営業とする基本的商行為に属する取引の
申込に限定するべきであるとの見解を示し、多数説によった場合の結果に対して批判的である。 (国際取引法要説より抜粋)
有力説:限定した範囲において本人の常居所地法ないし営業地法による
多数説を批判する有力説は、契約の要素をなす申込とか承諾とかの意思表示自体の成否の問題は、
契約自体の問題と区別して判断し得ないわけではなく、契約の実質の準拠法とは別個の準拠法によるべきであるとする。
よって、本人の常居所地法ないし営業地法によるべきであるとする。
従って、有力説の立場に立った場合であっても、意思表示の成否と意思表皮の効力発生時の問題以外の
意思表示に関する問題については、多数説と同様に契約の実質の準拠法により解決することになる。 (国際取引法要説より抜粋)
(2)ニューヨーク
連邦並びに州国際私法においいぇ、申込及び承諾を契約から分離して取り扱うことはしていない事から見て、
申込及び承諾の問題も、日本の多数説と同様に、契約の実質の準拠法によるものと見られる。
(3)ロンドン
英国国際私法においては、申込及び承諾を契約から分離して取り扱うことはしていないことから見て、
申込及び承諾問題も、日本の多数説と同様に、契約の実質の準拠法によるものと見られる。 (国際取引法要説より抜粋)
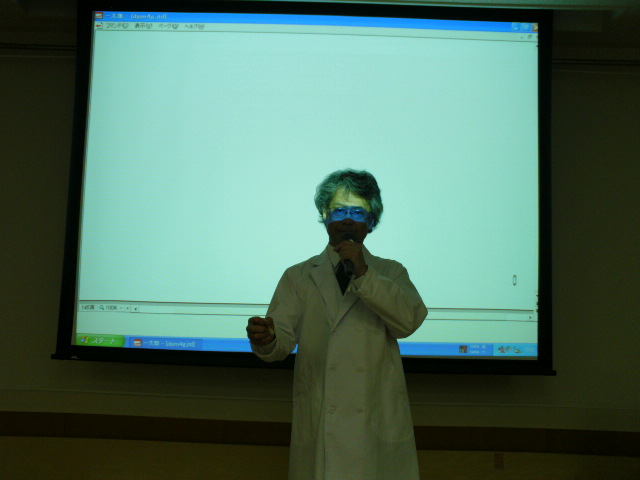
次に契約の成立の準拠法について説明する。
NEXT